ドリブル上達のたった一つのコツ!ドリブルの悩みはこれで解決!
ドリブルが上手くなりたい!でも…
・ドリブルの本を読んだり、プロのプレーを見て勉強しているけど、上手くいかない。
・ドリブルをすると、「持つな!」と怒られる。
・1対1の練習では自信をもってできるのに、試合になると自信がなくなってしまう。
・色々なボールタッチやフェイントを練習しているけど、試合になるとできない。
こんな風に悩んでいないでしょうか?上手くなりたいが故の悩みですよね。実は、このような悩みのほとんどが、たった一つのコツによって解決します。
それは、正しい基本技術を身につけることです。
「基本技術なんて、とっくに身についているよ」と、拍子抜けしてしまったかもしれませんね。
確かに基本練習は、サッカーを始めた頃からずっと行っていると思います。しかし、それは本当に正しい基本技術でしょうか?正しい基本技術とは何でしょうか?
ボールタッチ?ステップワーク?フェイント?
いえいえ、もっと根底になる考え方があります。それを理解しなければ、ボールタッチも、ステップワークも、フェイントもすべて見せかけの技術になってしまいます。(それなりのレベルでは通用するかもしれませんが)
本当に上手くなるには、正しい基本技術を理解し、正しい基本技術を身につけることが一番のコツです。
このページでは、ドリブル上達のコツである正しい基本技術について解説していきたいと思います。
ドリブル上達のコツ1:正しい基本技術を身につけるための3つのポイント
ドリブルの基本技術とは何でしょうか?これには、元日本代表MFの風間八宏さんの理論がヒントになります。
風間さんは、ドリブル上達のコツとして3つのポイントを挙げています。
1.ボールと自分の体を自由に操る
1つ目のコツは、ボールコントロールと身のこなしです。
鬼ごっこでは、素早い身のこなしができると、鬼の逆を取って逃げられます。ドリブルも同様に、素早い身のこなしができると、ディフェンスの逆を取ることができます。
ドリブルでは身のこなしにボール扱いが加わります。ボールを意識せず、体の一部のように自由に扱える技術が必要になります。
素早い身のこなし×ボールコントロール=ドリブルのボールタッチです。
身のこなしだけでも、ボール扱いだけでもダメです。両方できて初めてドリブルの技術になるのです。
実戦では、考えながらボールや体を動かしている暇はありません。ボールや体の動かし方に意識を向けるのは最低限に抑え、状況判断に意識を向けられるようにボールタッチを磨きましょう。
2.いつでも何でもできる場所にボールを置く
2つ目のコツは、ボールの置き場所です。ドリブルにおいて、ボールと体の位置関係は非常に重要です。
ボールが体から離れ過ぎていると、すぐにボールに触れません。ボールが離れた状態でディフェンスに寄せられてしまったら、成す術もなくボールを奪われてしまいます。
逆にボールが足元に入り過ぎると、ステップを踏みにくいので、スムーズに動き出せません。この状態では、ディフェンスを抜くことはできないでしょう。
ドリブル時は、いつでも何でもできる場所にボールを置くことが大切です。「この場所にボールを置けば、どの方向にも動けて、パスもシュートもできる」という場所を見つけてください。
それと同時に、体の使い方も重要です。体がいつでも何でもできる体勢になっているからこそ、ディフェンスの先手を取って動くことができるのです。
メッシ選手が細かいタッチのドリブルをしているので、それを真似して細かいタッチのドリブルを練習している人がいますが、細かいタッチだけ真似しても上達しません。
メッシ選手は、細かくボールを触ることで、いつでも何でもできる場所に常にボールを置いています。
また、ワンタッチごとに体の準備も整っているので、すぐに次の動作ができます。
だから、簡単に相手の重心の逆を取って突破することができるのです。
細かいボールタッチを練習する前に、まずはボールの最適なボールの置き場所と体の使い方を身につけることが先決です。
常に最適な場所にボールを置けていれば、別にタッチを細かくする必要は無いのです。
「なぜボールタッチを細かくするのか?」を理解せずに、見た目だけ真似しても、本当の技術にはなりません。
最適なボールの置き場所のヒントは、利き足です。世界のトッププレーヤーは、常に利き足の前にボールを置いてプレーしています。
この「利き足のポイント」は、17歳でサッカーを始め、ブラジルでプロになった檜垣裕志さんが提唱している理論で、私はサッカーの本質を突いた理論だと思います。両足信仰が根強い日本ですが、徐々に認知されてきています。
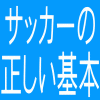
元日本代表の金田喜稔さんも、利き足のポイントを推奨しています。
3.相手を操る
3つ目のコツは、相手を操ることです。簡単に言えば、フェイントですね。
風間八宏さんのDVD「フットボールクリニック Vol.2」では、「相手を操る=相手に矢印を出させる」という表現を使っています。
例えば、ボールを持ったプレーヤーが右に行く素振りを見せれば、ディフェンスは右に重心を移動します。これが矢印が出た状態です。
オフェンスは、ディフェンスの矢印と反対にボールを運べば、ドリブルで抜くことができます。
サッカーでは、ボールを持ったプレーヤーに全ての主導権があるため、ディフェンスは、ボールを持ったプレーヤーのちょっとした動きにも反応します。ディフェンスを操るには、ちょっと右に重心をかけるだけでいいのです。
このことが分かっていれば、ドリブルで抜くことなんて簡単に思えませんか?
なぜ、こんな簡単なことを多くのプレーヤーができないかというと、ボールを持つ技術が身についていないからです。
技術がないから、ボールを持っても余裕がなく、早く決着をつけようと焦ってしまいます。勝負を焦ると、ディフェンスの矢印が出ていないうちにボールを動かしてしまうので、ディフェンスに反応されてしまいます。ボールを持つ技術があれば、余裕があるので、相手の矢印を感じ取ることができます。
では、ボールを持つ技術とは何かというと、正にここまでにお話ししてきた、ボールの置き場所、体の使い方、ディフェンスとの間合いです。
トッププレーヤーは、いつでも何でもできる場所にボールを置き、いつでも動き出せる体勢を作り、ディフェンスの足が届かない間合いでボールを持つことができています。だから、落ち着いてボールを持つことができ、ボールを奪われず、隙があればディフェンスを突破することもできます。
難しいフェイントを練習するよりも、まずはボールを持てる技術を身につけることが先決です。(本当にボールを持てる技術が身についている日本人プレーヤーは、アマチュアレベルでは皆無です)
ボールを持てる技術のヒントは、繰り返しになりますが、檜垣裕志さんの利き足のポイントにあります。利き足のポイントを詳しく学びたい方は、檜垣裕志さんのDVD教材「サッカーテクニック向上メソッド」がおすすめです。教材の内容は、レビューをご覧ください。

ドリブル上達のコツ2.DFを直視しない
ここから紹介するコツは、あくまでも補足的なものです。一番大事なコツは、正しい基本技術を身につけることです。そのことを理解した上で読み進めてください。
ドリブル時にはディフェンスを直視しないこともコツです。優れたドリブラーは、目の前のディフェンスを関節視野でとらえています。
「ボールを関節視野でとらえてドリブルする」というのは聞いたことがあると思いますが、「デイフェンスを関節視野でとらえる」とはどういうことでしょうか?
優れたドリブラーは、ドリブルするときにどこを見ているのでしょうか?ドリブルデザイナー岡部将和さんのインタビューで、デイフェンスを関節視野でとらえるコツが語られていました。
—ドリブルの最中、見て、意識してから動いたのでは間に合わないということですが、岡部さんご自身は、プレー中は何を意識して、どこを見ているのですか?
岡部 一人目のディフェンダーを抜いたあとに、二人目がカバーに来るのかどうかとか、パスができる場所はどこかとか、抜いた後にシュートをどこに打とうかとか、周囲をぼんやりみながら、先読みしながらプレーしていますね。つまり、目の前のディフェンダーのことはほとんど見ていません。というのも、一人目は視野に入れておきさえすれば、どんな反応をされても、判断を間違えなければ必ず抜けますから。
—一人目を抜くことは、ほとんど自動化されているということですか?
岡部 そうですね。サッカーでは「間接視野」という言葉を使いますが、ボールや人を直視するのではなく、間接視野で周囲をぼんやり捉えつつ、危ない領域にディフェンダーが入ってきたら、オートで間合いを取る動きを発動するイメージです。
(引用:誰にも止められないドリブルの極意)
優れたドリブラーは、ドリブルで抜くのを目的にしているのではなく、その後のパスやシュートにつなげる手段としてドリブルを使っているのです。
私も数少ない経験ですが、いいドリブルができたときは、目の前のディフェンスをほとんど意識していませんでした。その後のパスやシュートのイメージがあり、そのためのコースを作ることを意識してドリブルしていたのです。
すると、変な力みが取れて、自然体でドリブルすることができます。「抜くぞ、抜くぞ」とディフェンスを意識し過ぎると、力みが出て上手くいかないものです。運よく抜けても、その後のプレーにつながらないことがほとんどです。
ディフェンスを関節視野でとらえられるようになるには、ドリブルの基本技術が備わっていることが大前提です。関節視野を意識するというよりも、「技術があるから自然とできてしまう」という感覚だと思います。
ドリブル上達のコツ1で紹介した3つのポイントを、しっかり身につけることが大切です。
ドリブル上達のコツ3.手を使う
ドリブルを成功させるには、手を上手く使うこともコツです。
手を使うことで、ディフェンスをブロックしたり、死角にいるディフェンスの位置を確認することができます。
メッシ選手、アグエロ選手、テベス選手など、アルゼンチンの選手は手を使ったドリブルが得意です。
彼らはドリブルでかわした後に、腕を広げてデイフェンスを牽制します。こうすることで、ディフェンスにボールを奪うセカンドチャンスを与えないのです。
「手で相手を抑えるのはファウルなのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、サッカーのルールブックにはこう書いてあります。
競技者が次の7項目の反則のいずれかを不用意に、無謀にまたは過剰な力で犯したと主審が判断し場合、直接フリーキックが相手チームに与えられる。
・相手競技者をける、またはけろうとする。
・相手競技者をつまずかせる、またはつまずかせようとする。
・相手競技者に飛びかかる。
・相手競技者をチャージする。
・相手競技者を打つ、または打とうとする。
・相手競技者を押す。
・相手競技者にタックルする。
「不用意に、無謀にまたは過剰な力」は主審のさじ加減になりますが、ディフェンスを手で触る、ディフェンスを牽制する程度では通常はファウルにはなりません。
手をうまく使えるのも、ドリブル上達のコツ1で紹介した3つのポイントがしっかり身についていることが大前提です。基本ができていないと、ボールを持ったときのバランスが悪くなるので、手を使ってもディフェンスを牽制する効果はありません。
繰り返しになりますが、基本技術を身につけること最優先です。
まとめ
今回は、ドリブル上達のコツについてお話してきました。
ドリブル上達に大切なのは、複雑なフェイントを練習することではありません。何よりも大切なのは、基本となる3つのコツをしっかり身につけることです。
1.ボールと自分の体を自由に操る
2.いつでも何でもできる場所にボールを置く
3.相手を操る
複雑なフェイントは、練習すれば誰でもできるようになります。しかし、自分よりレベルの高いディフェンスには、まず通用しません。そもそも、フェイントすら使わしてもらえないでしょう。
ネイマール選手がトリッキーなフェイントを使いますが、正しい基本が高いレベルで身についているからできるのです。その根底にある部分を見ずに、見た目だけを真似しても上手くはなれません。
正しい基本技術が身についているかどうかが、プレーヤーのレベルにそのままつながります。基本ができているかどうかで、どのレベルでプレーできるかが決まるのです。
ドリブルは人気のあるプレーなので、ドリブルに関する本やDVDは数多く出ています。
しかし、ドリブル上達の本質を突いたものはわずかしかありません。ほとんどが枝葉の部分の解説に終始しています。
当サイトでは、数あるドリブル教材の中から、ドリブルの基本を身につけるのに最適なDVD教材を厳選しました。

ドリブルの正しい基本技術を学び、本当にドリブルの上手いプレーヤーを目指してください。
こちらの記事も読まれています


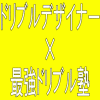






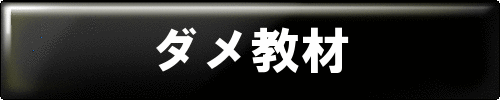



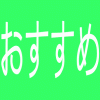

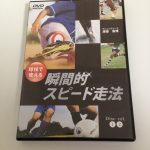
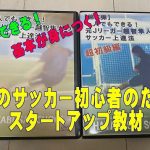
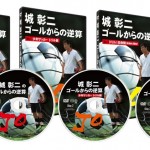


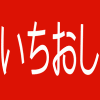



コメントする
この記事へのコメントはありません。