ドリブルで逆をとるための2つのポイント

相手の逆をとって完全に置き去りにする!
ドリブルで一番気持いい瞬間ですね。
相手の逆をとるには、複雑なフェイントは必要ありませんし、身長も足の速さも関係ありません。
では、相手の逆をとるドリブルは、どんなことに気をつければいいのでしょうか?
今回は、風間八宏さんの「FOOTBALL CLINIC Vol.2」、「JSC CHIBAの最強ドリブル塾」を参考に、相手の逆をとるドリブルのコツと効果的な練習法を考えていきたいと思います。
相手に矢印を出させる
逆をとるドリブルの1つ目ののポイントは、相手に矢印を出させることです。
「矢印」とは、風間八宏さんがよく使う言葉ですが、「重心の動き」を指しています。
相手の逆をとるには、相手が出した矢印と逆方向にドリブルすればいいわけです。
しかし、相手が矢印を出すのをただ待っているだけでは、いつまで経っても出してはくれません。
まずこちらがアクションを起こし、相手を食いつかせる必要があります。
相手に矢印を出させる方法は、大きく分けて2つあります。
誘いのドリブルとフェイントです。
誘いのドリブル
誘いのドリブルとは、DFの心理を利用したドリブルで、JSC CHIBA監督の川島和彦さんが「最強ドリブル塾」の中で説明しています。
DFの心理として、ボールを持ったプレーヤーが離れて行くと、DFは追いかけます。
逆に、ドリブルで向かってくるプレーヤーに対しては、DFは止まって構えます。
つまり、相手に向かっていくのではなく、相手がいないスペースにドリブルすることで、相手を誘い出し、矢印を出させることができるのです。
この心理が分かると、相手を誘い出してかわすプレーが意図的にできるようになります。
メッシ選手は、サイドから中央へ切り込んでいくドリブルが得意です。
このドリブルもDFの心理を利用し、DFを縦に誘い出してから中に切り返しています。
フェイント
これに対し、フェイントは、相手と正対したときに有効な方法です。
相手と正対し、お互いに相手の出方をうかがっているときは、相手のちょっとした動きにも敏感に反応します。
そこで、フェイントが有効になります。
ネイマール選手は、こういった場面でボディフェイクやシザースなど、ボールに触らないフェイントをよく使います。
ボールを動かしていないので、どの方向へも持ち出すことができます。
相手が体の動きにつられて矢印を出してくれれば、いつでも逆をとることができるのです。
切り返しのアイディア
相手の矢印が出たら、それと逆方向に切り返せば逆をとるドリブルの完成です。
切り返すときは、相手が残り足を出してくることもあるので、相手の足にボールを引っ掛けないようにすることが大切です。それが2つ目のポイント、切り返しのアイディアです。
ボールを引っ掛けないようにするには、次のような方法があります。
- タイミング
- 間合い
- 切り返しの角度
- 切り返しの工夫
相手の足が出てくるよりも先に切り返す
相手の足が届かない間合いで切り返す
マイナス方向に切り返せば、相手の足が届かない
ボールを浮かす、股抜き、軸足の後ろを通す(クライフターン)
ドリブルデザイナー岡部将和×最強ドリブル塾で「間合い」を極める
逆をとるドリブルの練習法
ここまでは、逆をとるドリブルの理屈を述べてきましたが、いくら理屈が分かっても練習しなければできるようにはなりません。
「相手に矢印を出させる」、「切り返しのアイディア」という2つのポイントを身につけるには、やはり対人練習が一番です。
ドリブルの対人練習の基本は1対1ですが、「JSC CHIBAの最強ドリブル塾 ディスク1」では、少し工夫を加えた1対1を行っています。
これは見ているだけでも勉強になるので、研究熱心な人にはおもしろいと思います。

DFに条件をつけることで、ディフェンスの対応に応じた抜き方を練習できる
(JSC CHIBAの最強ドリブル塾より)
どういう1対1かというと、DFに「ある条件」をつけて行います。
この条件により、DFはボールの取り方が限定されます。
条件は2種類あり、オフェンスはDFの対応の仕方に応じたドリブルを練習することができます。
ただし、DFがどういう対応をしてきても、逆をとるドリブルの2つのポイントは変わりません。
相手に矢印を出させるタイミングやアイディアが違うだけです。
最強ドリブル塾は、川島さんが監督を務めるJSC CHIBAの練習の様子がそのまま収録されているので、色々な選手のドリブルを見ることができます。
DVDの中には、逆を取るのが上手い選手もいれば、苦手な選手もいます。
上手い選手は、DFの対応の仕方に応じて矢印を出させるタイミングやアイディアを使い分けていました。
このように成功例と失敗例を見比べて、何が違うのか考えながら見ることで、ドリブル上達のヒントを得ることができます。
練習ももちろん大事ですが、このように客観的に見て考えることも上達するための重要な時間だと思います。


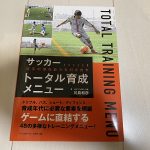

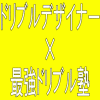


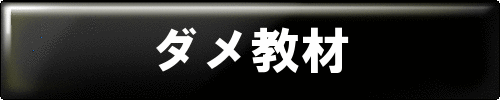



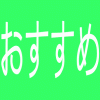

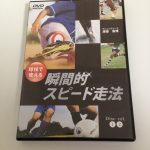
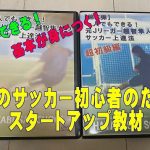
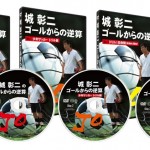


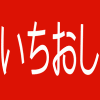





コメントする
この記事へのコメントはありません。