抜くドリブルのコツと練習法 40歳からでも上手くなれる!

「ボールを取られるのが怖いので、パスに逃げてしまう」
「周りから文句を言われるので、ドリブルできない」
「歳を取るごとにドリブルができなくなってきた」
ドリブルでDFを抜いた瞬間は、何とも言えない爽快感があり、サッカーの醍醐味でもあります。戦術的に見ても、ドリブルで抜ければ、相手が1人減って数的優位が作り出せるので、効果的なプレーです。
しかし、人間30代半ばを過ぎると筋力やスピードの衰えを感じ、だんだんドリブルで抜けなくなったり、そもそもドリブルしようという意欲がなくなってきたりします。
また、大人になってからサッカーを始めた人は、周りから「ボールを持つな!」と言われ、ドリブルすることに罪悪感を持ってしまう人もいます。

ドリブルはセンスのある人やスピードのある若い人の特権と思っていませんか?
実は、ドリブルはポイントを押さえて練習することで、誰でも、何歳になっても上達することができます。この記事では、抜くドリブルのコツと練習法をお伝えしていきます。
パスを受ける前に相手との間合いを把握する
ドリブルに限った話ではありませんが、パスを受けるときにトラップしてから「何をしようか」と考えているようでは、試合では通用しません。

優れたプレーヤーは、ボールが来る前に周りの状況を見て、次のプレーをイメージしています。
ドリブルについて言えば、パスを受ける前に、自分をマークしている相手の間合いを把握することが大切です。近くに寄せられているのか、フリーでボールを受けられるのかを、パスを受ける前に把握しておきます。
さらに寄せられている場合は、どこまで相手が近づいているのかを把握します。ファーストタッチで前を向けるのか、背負ってトラップしなければならないのか。もし相手が突っ込んでくるのが分かれば、ファーストタッチで大きめにボールを出して、DFの裏を取ることもできます。
パスを受ける前に、相手との間合いを把握する。これを大前提として話を進めていきます。
勝負はボールを持つ前から始まっている

ドリブルを使うには、まずドリブルで仕掛ける体勢を作る必要があります。パスを受けたときに、相手にガッツリ寄せられて前を向けない状態では、ドリブルすることができません。
相手とある程度の間合いを確保し、前を向いてボールを受けるためには、ボールを持つ前の駆け引き、いわゆる「オフザボールの動き」がポイントです。
パスを受ける時に、まず初めに狙うべきなのは、DFの裏を取ることです。DFの裏でパスを受けられれば、ドリブルでDFを抜いたのと同じことなので、わざわざドリブルを使う手間が省けます。
DFは、自分の裏を取られることを一番嫌がります。まずオフザボールの段階でDFに「裏を取られる」という危機感を与えることが大切です。裏を狙って走ると見せかけ、キュッとターンすれば、相手との間合いを作り、余裕を持って足元でパスを受けることができます。
ドリブルで抜けるかどうかはファーストタッチで決まる

オフザボールの駆け引きでフリーになることができたら、次はファーストタッチでのボールの置き場所です。

ファーストタッチできちっとボールを置けるかどうかで、勝負の8割は決まる!それくらい重要な段階です。
利き足の前にボールを置く
ボールの置き場所の基本は、利き足の前です。利き足でコントロールしやすい場所にボールを置くからこそ、プレスを受けてもバランスを崩さず、落ち着いてかわすことができます。
日本では、「左右均等にボールを扱う」という考え方が一般的です。「右サイドでは右足で、左サイドでは左足でボールを持つ」と教えている指導者もいますが、私はこれは間違いだと思います。
プレッシャーのかかる試合では、人間は自然と利き足に頼ります。世界のトッププレーヤーを見ると一目瞭然で、メッシ選手、イニエスタ選手、ネイマール選手などは、みんな利き足を中心としたボールの持ち方をしています。

誤解されやすいのですが、「逆足を使うな」ということではありません。
トラップで逆足を使うこともありますし、右利きで左サイドを縦に突破したら、左足でクロスを上げることになります。シュートも左右両方で打てた方がいいに決まっています。
重要なのは、「利き足を中心としたボールの持ち方」を意識することです。「左右どちらも」では、プレーのベースが定まらず、フワフワした状態になってしまいます。ドリブルの調子に波があるプレーヤーは、ベースとなるボールの持ち方がブレていることが多いのです。
⇒サッカーの正しい基本とは?檜垣裕志さんの利き足のポイントを考察
ボールの置き場所は人によって微妙に違う
先ほども言いましたが、パスを受けたときには次のプレーがイメージできていることが基本です。(もちろん、次のプレーのイメージは利き足中心で考えます。)次のプレーのイメージができていれば、ファーストタッチでボールをどこに置くかは自然と決まります。
さらに、相手DFのポジショニングや間合いも考慮する必要があります。相手がプレスをかけてきたなら、トラップを大きく出してかわすこともできます。相手のプレスが速くて五分五分の状況なら、体を壁にしてキープを考えなければいけません。
いつでも利き足で触れる位置にボールを置くのが基本ですが、その場所は個々で微妙に変わります。それは反復練習で、各自が見つけていくしかありません。具体的な練習方法は、後で紹介していきます。
抜くドリブルの基本形は2つ

ドリブル突破には色々なテクニックがありますが、基本形は「緩急」と「逆取り」の2つに集約されます。
緩急で抜く
ドリブルしているときに急に止まると、相手もそれに合わせて止まります。この相手が止まる瞬間を予測し、再び加速すれば、相手よりも一歩前へ出ることができます。
ポイントは、「緩」から「急」に加速するタイミングを相手に合わされないことです。相手がスピードを落とそうとカカトをつく瞬間に、グンッと加速します。相手がスピードを落とす瞬間を見極める感覚が必要です。
逆取りで抜く
「逆取り」は簡単にいえば、右へ行くフリをして左へ行く。それだけのことです。
もっとも簡単なフェイントはボディフェイントで、右サイドでボールを持っているとき、右足をグッと縦方向に踏み込むと、DFはそれに反応して重心が縦方向に移動します。
そこからオフェンスは右足で地面を蹴って、左足のアウトで中央へボールを持ち出します。DFはそれを見てから中央へ重心を移動するため、自分の足のすぐ横を通るボールに反応できません。

かつてグランパスで活躍したストイコビッチさんは、このプレーが得意でしたし、メッシ選手もボディフェイントを多用します。
ボディフェイントの他にも、ボールをまたぐシザースなどが、逆取りのフェイントとしては有名です。
いくら逆方向に相手の重心をずらしても、そこからボールを持ち出すのが遅くなると、重心を立て直したDFにカットされる恐れがあります。相手をだましながら、速さも兼ね備えているのが、良いフェイントといえます。そのためには、体幹の強さや瞬発力を鍛えていくことも大切です。
自分の得意な形を見つける
ドリブルで抜くコツとして、自分の得意な形を見つけることも大切です。
三苫薫選手といえば、今(2021年6月現在)Jリーグを代表するドリブラーの1人です。
三苫選手は、左サイドでドリブルを仕掛けるときに得意な形があります。利き足である右足の前にボールを置き、緩急を使って相手のタイミングをずらし、右足のインサイドで縦へ突破する形です。自分のスピードを活かした抜き方ですが、この形になるとDFは分かっていても止められません。
特にチームが相手陣内に押し込んでいて、足元でパスを受けたときにこの形を多用しますが、このときのパスの受け方も、この形に持ち込むことから逆算した受け方をしています。つまり、意図的に自分の得意な形に持ち込んでいるということです。
自分の得意な形を持っていると、そこから色々な応用を利かすこともできます。三苫選手の例でいえば、縦へ突破すると見せかけ、カットインするというパターンもあります。得意な縦突破をフェイントにした応用技です。
自分の得意な形は、なんとなく練習しているだけでは見つかりません。対人練習で自分の抜きパターンを分析するなど、考え、意識することで見つかります。また、プロ選手のプレーを研究することで、ヒントを得られることもあります。
抜くドリブルを身につける練習法
抜くドリブルの練習法として、ここでは技術、フィジカル、対人という3つのカテゴリーに分けて紹介します。
技術練習
技術練習は、コーンドリブルなどの1人で行うドリルが中心です。ボールコントロールと体のコントロール(身のこなし)を向上させることが目的です。
たとえば、この利き足のイン・アウトは、利き足の前にボールを置くボールタッチとステップを身につけるのに効果的な練習法です。

ドリルは1人でも練習できるので、自主練で行うのがおすすめです。(チーム練習では、複数人必要な練習をした方がいいです。)
特に、みんなで集まって練習する機会の少ない社会人プレーヤーは、ボールと体の感覚を養う(上級者は維持する)ためにもおすすめの練習法です。
「コーンドリブルは意味がない」という人もいますが、目的を勘違いしている人が多いです。コーンドリブルは、DFを抜くための練習ではなく、ボールと体のコントロールを高めるための練習です。ここを間違えると、意味のない練習になってしまいます。
コーンドリブルについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
⇒コーンドリブルで突破に必要なスピードを身につける方法
フィジカルトレーニング

抜くドリブルには、素早く体を動かせることも大切な要素です。そのためには、体幹の強さや瞬発力を鍛えていく必要があります。
人間の筋肉量は、20歳ごろを過ぎると少しずつ減っていきます。しかし、20代の頃はあまり気づきません。「何か違うな」と思うようになるのは、30過ぎからです。若い頃はバリバリのドリブラーでも、30を過ぎると思うように抜けなくなる人が増えてきます。
だから、社会人プレーヤーはボールテクニックだけでなく、フィジカルトレーニングで基礎体力を維持していくことも大切です。特別な器具を使う必要はなく、家トレでも十分です。
ドリブルに役立つフィジカルトレーニングは、こちらの記事で詳しく解説しています。
⇒ドリブルのキレを上げる4つのポイントと練習法
対人練習
抜くドリブルには、間合い、ボールの置き場所、仕掛けの形、相手との駆け引きなどの対人スキルを高める必要があります。これらは、対人練習で身につけていきます。
対人練習の基本は1対1です。一般的な1対1は下の動画のような形ですが、色々と条件を付けることで、練習の目的を絞ったり、より実戦的な設定にすることができます。
1対1については、こちらの記事で詳しく解説しています。
⇒抜くドリブルに必要な間合いを養う練習法
⇒ドリブル練習の1対1は意味がない?1対1が劇的に変わる4つのポイント
ドリブル練習におすすめのDVD教材
「自主練習をやっているけど、本当に上手くなっているのか分からない」
「ドリブルが上手くなるには、どんなことを意識して練習すればいいのか分からない」
「ドリブル練習は、1人でやっても意味がないんじゃないの?」
という人は、わんぱくドリブル軍団 JSC CHIBAの最強ドリブル塾がおすすめです。

最強ドリブル塾は、1人でできるドリルから対人練習まで、ドリブル上達に必要な練習が総合的に紹介されたドリブル専門のDVD教材です。
講師のJSC CHIBA代表の川島和彦さんは、ドリブル指導に定評がある指導者で、少年サッカー界ではちょっとした有名人です。その練習メソッドは大人にも通用します。ベテラン指導者の実証済みの方法を取り入れることで、いつもの練習が、より効果的なものにブラッシュアップされます。
社会人プレーヤーの場合、自主練で対人練習を行うのは難しいかもしれませんが、対人練習の映像を見ることで、イメージトレーニングにもなります。
当サイト経由で公式ページから購入すると、オリジナル特典(どーな特典)が付きます。
- 90日間返金保証
- どーな特典:最強ドリブル塾「裏」マニュアル~30分で最強ドリブル塾のキモがわかる本~
※決済画面で「どーな特典」が表示されていることを確認してください。
「最強ドリブル塾」のレビューはこちら!
⇒日本一詳しい!わんぱくドリブル軍団 JSC CHIBAの最強ドリブル塾のレビュー
まとめ
抜くドリブルのコツ、練習メニューを紹介してきました。最後にまとめておきます。
- パスを受ける前に、自分をマークしている相手との間合いを把握する
- オフザボールの動きで、ドリブルで仕掛ける段取りを整える
- ファーストタッチで利き足の前にボールを置き、何でもできる状態を作る
- 緩急で抜く場合は、相手がスピードを落とすタイミングで加速する
- 逆取りで抜く場合は、相手を騙しながら、速さも兼ね備えたフェイントを使えるようにする
- DFが分かっていても止められない自分の得意な形を見つける
- 抜くドリブルの練習法は、大きく分けて技術練習、フィジカルトレーニング、対人練習がある
- ドリルでボールと体のコントロールを高める
- 人間の筋肉量は20歳から少しずつ減っていくので、社会人プレーヤーにはフィジカルトレーニングは必須
- 対人練習で間合い、ボールの置き場所、仕掛けの形、相手との駆け引きを養う
- わんぱくドリブル軍団 JSC CHIBAの最強ドリブル塾は、ドリブル上達に必要な練習法がまとめられたドリブル専門DVD教材
- 日本一詳しい!わんぱくドリブル軍団 JSC CHIBAの最強ドリブル塾のレビューはこちら
当サイトおすすめのドリブル教材まとめ
⇒サッカードリブル練習DVDおすすめ4選





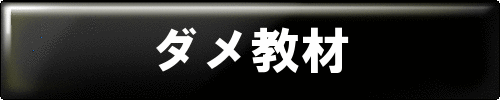



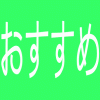

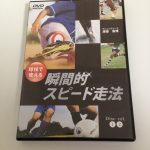
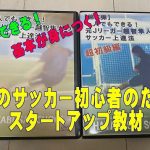
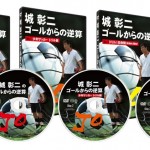


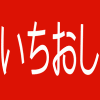




コメントする
この記事へのコメントはありません。